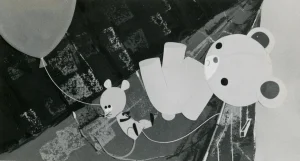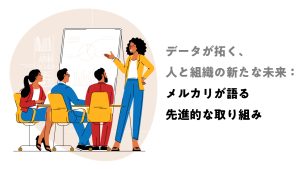最近、さまざまなフルーツ入り大福などそのバリエーションが増えている大福餅。もとはといえば、江戸時代の江戸で生まれた江戸っ子グルメでした。そして江戸時代から戦前にかけての大福餅は、現在とは異なる食べ方をしていたのです。今回は、大福餅の歴史について食文化史研究家の近代食文化研究会さんが解説します。
巣鴨名物 塩大福
おばあちゃんの原宿、巣鴨地蔵通商店街。

毎月四のつく日(4・14・24日)の縁日には、商店街は多くの屋台と人出でにぎわいます。そして縁日の日にいつも行列ができるのが、「みずの」「伊勢屋」という二つの和菓子屋。

お客さんのお目当ては、何と言っても巣鴨名物の塩大福。

優しい甘みにほんのりとした塩味がマッチする、何度食べても食べ飽きない味。リピーターが多く、行列ができるのも納得です。
江戸時代の江戸で生まれた大福餅
この大福餅が、アメリカに進出しているというのはご存知でしょうか?
アメリカのスーパーマーケットで売られている「モチアイスクリーム」(Mochi ice cream)は、餅皮でアイスを包んだお菓子。つまりロッテ「雪見だいふく」の類似商品であり、いわば大福餅の孫にあたる商品です。

塩大福、「雪見だいふく」だけでなく、多種多様なフルーツ大福など、さまざまな派生品に進化し続ける大福餅。実は大福餅は、もとはといえば江戸時代の江戸で食べられていた、冬の屋台グルメだったのです。
江戸時代の百科事典『嬉遊笑覧(きゆうしょうらん)』によると、大福餅の祖先は「うずら焼」。赤小豆の塩餡を包んだ、鳥のウズラに似た丸っこい「うずら焼」が後に「腹太(はらぶと)餅」と名を変え、さらに砂糖味のこし餡になって名前も「大福餅」に変化したのだそうです。

この絵は天保年間に描かれた『江戸名所図会』の大福餅の屋台。左上の鉄板で大福餅を焼いています。
このように大福餅は、もともとは屋台の食べ物。モチアイスクリームとは真逆の、焼きたて熱々を食べる、冬の路上のお菓子だったのです。
人力車夫のエネルギー源だった明治時代の大福餅
大福餅は明治時代以降も、屋台で焼いて売っていました。
“ここら(浜町)の近くでは、両国橋や大橋のたもとの特定の場所にいつも屋台が出ていました。季節でいえば、これは秋から春先までのもので、ぽかぽか陽気の頃、食べたいと思うものじゃない。焼き大福は、炭火の上に鉄板を乗せて、こんがり両面を焼いて、餡まで熱くなっているものを、ふうふういいながら食べるもので、もとより、上品なお菓子ではない。”(森義利『幻景の東京下町』1989年刊)
これは版画家・森義利による、昭和初期の東京下町の大幅餅屋台の描写。焼いた熱々の大福餅は、寒い時期にありがたいものでした。

これは明治時代の大福餅屋台。向かって左に人力車夫の姿があります。
“橋のたもとで売っていたのは、そこが人の往来が激しいところだったせいですが、その人の往来というのも、若い肉体労働者が多かったということにも関係があると思う。”(森義利『幻景の東京下町』1989年刊)
大福餅は、人力車夫などの肉体労働者のエネルギー源となっていました。ちょうどマラソンランナーが走りながらバナナで栄養補給するように、人力車夫などの肉体労働者は、大福餅で栄養補給しながら働いていたのです。
戦前の塩大福とは
そんな肉体労働者向けの、特別な塩大福も売られていました。
“大福には甘餡と塩餡とがあり、 どちらも二銭だったが、塩の大福はばかにでかかった。”
”真っ黒い火入れの上に鉄板を置き、大福 とか三角形の餅などをちょうど食べごろに焼いていた。ここに集まる定連は、車力、馬力、小僧さん、行き交う労働者などで、ここは一息入れる憩いの場所であった。”(野口孝一『明治の銀座職人話』1983年刊)
これは明治時代の銀座の大福餅屋台の描写。 人力車夫(車力)などの労働者向けに、“ばかにでかかった”塩大福が売られていました。
この塩大福、巣鴨の塩大福とは異なり、砂糖の入ってない塩味だけの餡。
“直径は十二、三センチはあったかナ、厚さも相当ある。 しかし、餡には砂糖がはいってなくて、塩味の、いわゆる塩餡がタップリはいっていて、五銭 (大正末期)であった。”(玉川一郎『たべもの世相史・東京』1976年刊)
砂糖のコストを削り、その分の費用を大福餅そのものを大きくするために使ったのでしょう。肉体労働者がより高い満腹感をえられるように、大きさに特化した大福餅が、戦前の塩大福だったのです。